14.

わたしが何とか家についたとき、中で父が 「来るんじゃない、向こうへ行け」 とどなったのでわたしはびっくりしました。無残な黒こげの母をわたしに会わせたくなくて叫んだのでした。
当時町内会長だった父は近所の人と街に残りました。
15.


先に逃げた母を探して、表参道の通りを埋め尽くしている黒こげの遺体の中からようやく母を見つけました。
「この灯籠の脇で倒れていたみたいよ」
うつぶせに倒れ亡くなっていた母。唯一、お腹周りだけが焼け残りました。
「怖いというか見たくないというかあまり傍に近寄りたくないという気持ちがはじめは。いつもあった。だからあえてここは通らなかった」
16.「遺品展示で空襲の悲惨さを」


空襲を伝えたいと託した母の遺品。都に預けてから14年もの間触れられなかった母の面影。それを確かめたいと、遺品を一旦帰してもらいました。
「思い出しましたね。色々」「すごいですねこんな焼け焦げて」
ヘルメットをつけて逃げた母。お腹周りにつけていた小物入れや服の一部が焼け残りました。
「母の着物だわ。懐かしい」
17.
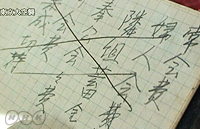

「母がどこそこへ何を送ったのだの。町会費とかそんなのが書いてあるから、そんなのの控えでしょう」
「この呼び子がね、リュックサックのどっかにくっつけてあった。それが父に目に触って見付かったって言っていた」